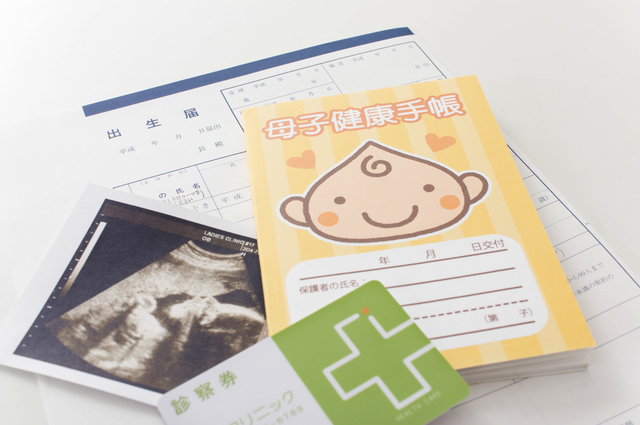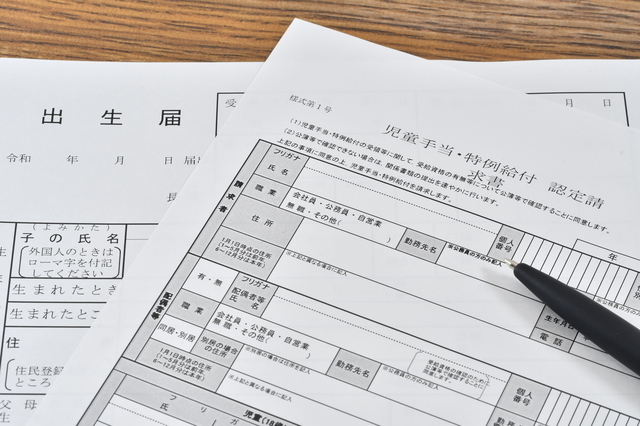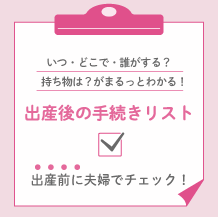手続きの準備は出産前に!
出産前の準備が大事!
出産してしばらくは、ママは赤ちゃんのお世話で忙しくなります。また、母体の回復には時間がかかるので体調も万全ではありません。
出産後に慌てることがないよう、手続きに必要な情報は出産前に確認しておくと安心です。
手続きによって申請先や申請期限が異なるので、しっかりチェックしましょう。
パパに協力してもらうのが◎
1ヶ月健診までは、ママも赤ちゃんも長時間の外出は控えたほうがよいと言われています。出産後の手続きは出来る限りパパにしてもらうようにしましょう。
パパが困らないように、必要な情報は事前に共有しておくといいですね。記事の最後にご紹介するリストを使えば、漏れもなくスムーズに手続きできますよ。
出産は家族で協力し合って乗り越える一大イベントです。手続きについても、出産前から家族でしっかりと準備をしましょう。
出産後にする主な手続き
出生届
生まれた赤ちゃんを戸籍に登録する手続きです。出生届の出生証明書の欄は病院で記入してもらうようになっています。
【手続き期間】
生まれた日から 14 日以内
※14日以内に手続きをしなかった場合、罰金を科せられる場合があります。
【手続き先】
役所
(父・母の本籍地、届け出人の居住地、出生地のいずれかの区市町村役場)
【必要なもの】
・医師または助産師が記述した出生証明書及び出生届
・母子健康手帳
・届け出人の印鑑
【届け出人】
父または母
健康保険
生まれた赤ちゃんを健康保険に加入する手続きです。国民健康保険の場合は住民票のある市区役所・町村役場に、社会保険や共済保険の場合はパパかママの勤務先への手続きになります。
共働きの場合はどちらでもよく、所得が高いほうでなければならないという決まりはないので、扶養に入れる側で手続きを行います。
国民健康保険
【手続き期間】生まれた日から 14 日以内
【手続き先】
居住地の役所
【必要なもの】
・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳
・請求者の個人番号(マイナンバー)確認書類
・身分証明書
【届け出人】
父または母
社会保険・共済等
【手続き期間】出生後速やかに
【手続き先】
勤務先
【必要なもの】
・申請書
・扶養者の本人確認書類
・扶養者と子どものマイナンバー
※勤務先に要確認
【届け出人】
父または母
児童手当
児童手当は、国から子育て支援の一環として、児童を養育する保護者に支給される手当です。
子どもが0歳から高校を卒業するまで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)支給されます。金額は子どもの年齢や人数により変化します。
児童手当金は届け出が遅れてしまうと、さかのぼって支給されないため、忘れずに申請しましょう。
【手続き期間】
生まれた日の翌日から 15 日以内
※出生届、乳幼児医療費助成の手続きも同時に行うのがおすすめ
【手続き先】
居住地の役所
【必要なもの】
・認定請求書
・請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
・請求者の健康保険証又は資格確認書(のコピー)
・請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
・本人確認書類
※その他状況により別途書類が必要となる場合があります。
【届け出人】
父または母
乳幼児医療費助成
子どもが病気やケガで医療機関を受診したときに、医療費を助成してもらえる制度の手続きです。
子どもの年齢や親の収入により助成内容が違うなど、自治体によって制度が異なります。乳幼児医療証の提示で医療費が無料になったり後日補助金で還付されたりする場合があるので、お住まいの自治体の制度を事前にチェックしておきましょう。
【手続き期間】
出生後速やかに
※出生届、児童手当の手続きも同時に行うのがおすすめ
【手続き先】
居住地の役所
【必要なもの】
・届け出人の印鑑
・乳児の保険証のコピー
※子どもと別世帯の者が手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類
【届け出人】
父または母
出産育児一時金・出産育児付加金
健康保険に加入していると、出産費用の一部(原則50万円)が給付される制度の手続きです。こちらも国民健康保険の場合は住民票のある市区役所・町村役場に、社会保険や共済保険の場合はパパかママの勤務先への手続きになります。
出産育児一時金はパパママが直接手続きするのでなく、病院が代わりにやってくれる「直接支払制度」が多くなっていますが、病院により異なりますのでチェックが必要です。
直接支払制度
【手続き期間】出産前
【手続き先】
産院
【必要なもの】
直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書
【届け出人】
出産する本人
通常
【手続き期間】退院後
【手続き先】
加入している保険協会(社会保険)
役所(国民健康保険)
【必要なもの】
・出産した本人の健康保険証
・母子健康手帳
・直接支払制度を利用しない旨を記載した合意書
・出産した医療機関などからもらう出産費用の領収・明細書
・世帯主の印鑑
・世帯主の振込口座がわかるもの
※死産・流産の場合は、医師の証明書
【届け出人】
出産する本人
その他の手続きは?
出産に関する手続きとしては、そのほかに以下のようなものがあります。
・赤ちゃんが未熟児だったとき:「未熟児養育医療給付金」
・ママが産休を取得するとき:「出産手当金」
・パパが産後パパ育休を取得するとき:「出生時育児給付金」
・ママやパパが育休を取得するとき:「育児休業給付金」
産後すぐに申請が必要なものではありませんが、それぞれに定められた申請期限があるので確認しておきましょう。
また、出産前に入院または出産時に帝王切開などの手術をした場合、民間の医療保険に加入していれば入院給付金や手術給付金を受け取ることができます。こちらも忘れずに手続きしましょう。
まとめ
以上、産後の手続きについてご紹介しました。
ママはできるだけ赤ちゃんのお世話と自分の身体の回復に集中できるよう、なるべく産後の事務手続きは事前に準備しておいてスムーズに終わらせたいですね。
特に里帰り出産の方は念入りにチェックをしておくのがおすすめです。ぜひ参考にしてみてくださいね。
・表示価格は、改正前の消費税率で掲載されている場合があります。ご了承ください。